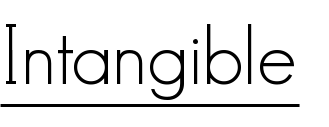|
東京オリンピックが開催された1964年からはや半世紀が過ぎました。私はオリンピックに格別の思い入れがあります。当時24歳、モスクワから帰ったばかりの私は民放放送のロシア語の通訳として、ソヴィエト選手と他の東欧諸国の全種目の通訳を仰せつかりました。あたかも東京は戦後の復興期で、数年前には皇太子殿下と美智子妃のご婚礼が祝賀ムードで盛り上がり、この年には新幹線の開業、高速道路の相次ぐ開通があり、国民は明るい未来に向け、一丸となって邁進していました。
米ソ冷戦のさなかで「鉄のカーテン」の向こうからやってきた選手団の動向にマスコミをはじめ各方面の関心が集まっていました。開催中にフルシチョフ首相が失脚したらしいという情報が本国から流れたのでしょうか、選手団に大きな動揺がひろがりました。通訳ならなにか知っているかもしれない、気が付くと、私のまわりに各国のマイクが取り囲んだことを覚えています。
このような世界情勢ではありましたが、東京の治安は安定していて、いまのようにテロなどを警戒する警察の姿もなく、ゴミ箱も設置されていて、人種間の隔たりやイデオロギーの違いなどみじんも感じられない和やかな雰囲気の中、オリンピックが開催されました。「参加することに意義がある」というインタンジブルなオリンピック精神はもちろんですが、それでもなんとか祖国のために「メダルを勝ち取りたい」というタンジブルな競技精神がどこまでも高まって、素晴らしい祭典となりました。
各大学の体育館は会場として大いに役立っていました。たとえば、駒澤大学、日本大学、立正高校など、カヌーは相模湖、ボートは戸田の競艇場でした。宇都宮の公園にも行った思い出があります。いまのようにオリンピックのために都民の血税で何千億円という単位のお金を使いません。オリンピック後のことを考えず、つぎつぎに会場を新設するなら、国民は新しい形の税金をかけられているのと同じです。国際オリンピック競技委員会が何から何まで開催地の現状や国情を十分把握しないまま、「助言」という名の下の指図をするのはいかがなものでしょうか。
1960年代はまだ、ファックスも、コンピュータもなく、携帯電話、スマホなどあるはずもありません。情報は手書きでデスクに、公衆電話や選手村の中の電話ボックスが唯一のニュースを知らせる手段で、選手村の中は自転車が移動手段です。なんと不便で何と美しく微笑ましい光景だったことでしょう。閉会式の電光掲示板に“さよなら、See you in Mexico”と文字が掲げられると、日本の技術の進歩に感動して胸が高鳴ったものです。そして「蛍の光」が流され、各国の選手が手を挙げて別れを惜しんだ光景は素朴そのもので世界の心がまさに一つになりました。
その50年の月日のあいだに何回も各国でオリンピックが開催されてきましたが、しだいにそのありようが変化してきました。派手な開会式は近代技術をこれでもかと見せつけ、タンジブルな趣向一辺倒。感動どころか、驚きはしても記憶に残るといったような感激はありません。世界中が成金ぶりを披露し、自国の技術を誇示し、あっと言わせることに躍起になり、なりふりかまわぬケバケバしさは馬鹿げているとしか言いようがありません。
「火を吹き、カネを喰らう怪物」になりさがってしまったオリンピック。まるで「開会式と閉会式のための祭典」のようです。オリンピックの精神などどこかに吹っ飛んでしまっています。
どこかの国がどこかの時点でスポーツの祭典の原点を再認識して、余分なものを取り除いてオリンピックの本来の精神にのっとった祭典にするならば、その国こそ最高の知性と文化を持ち得た国といえるでしょう。
タンジブル一辺倒のオリンピックから、あるべきインタンジブルな精神にむかってほしい。――これが私のオリンピックに対する心からの希望であり、メッセージです。
|